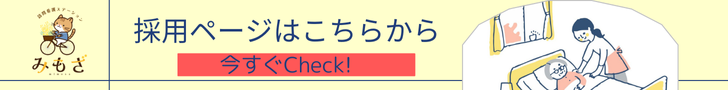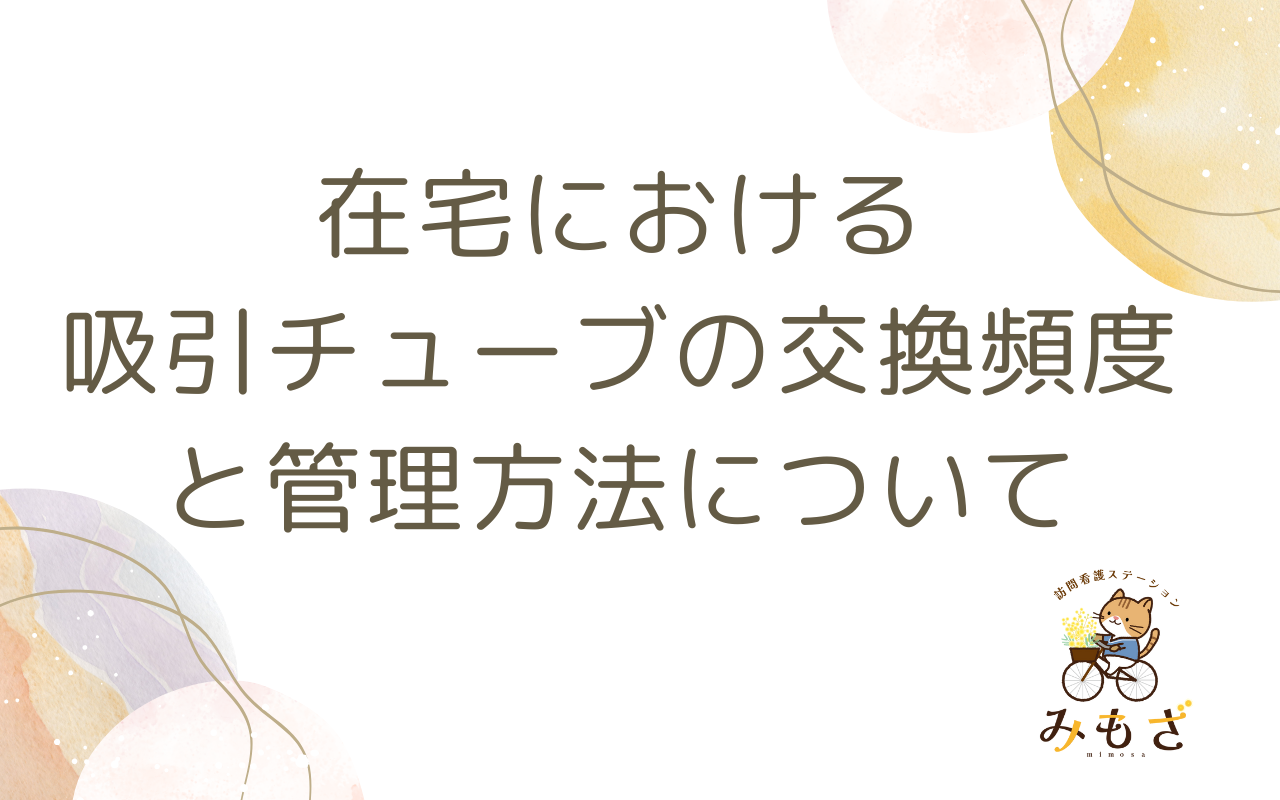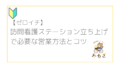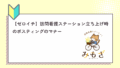病院では、シングルユーズで使用される吸引チューブですが、在宅ではクリニックから処方された本数やご家族で購入された本数であったりと、使用できる吸引チューブの数が限られてきます。
今回は、在宅での吸引チューブの交換頻度と吸引チューブの管理方法、在宅での収納術についてまとめてみました。
在宅における吸引チューブの交換頻度
病院では基本的には使用後速やかに破棄、再利用する場合でも1日に1回は交換をします。在庫に限りがある在宅ではどのタイミングで交換をしているのでしょうか?
気管内吸引に使用している吸引チューブの交換頻度
在宅で気管内吸引に使用する吸引カテーテルは、1回/日のペースで交換するケースがほとんどです。ただし、明らかに汚れている場合や破損している場合はその都度、交換をします。
口腔・鼻腔内吸引に使用している吸引チューブの交換頻度
在宅で口腔・鼻腔内吸引に使用する吸引カテーテルの場合は、1回/1~3日のペースでの交換がほとんどです。ただし、明らかに汚れている場合や破損している場合は速やかに交換をします。
在宅における吸引カテーテルの管理方法
再使用をする吸引チューブはどのように管理するとよいのでしょうか?
共通の再利用手順として
- 使用後のカテーテルの外側をアルコール綿またはティッシュで拭く。
- 清潔なカップに水道水を注ぎ、カテーテル内腔を洗浄する。
があげられます。注意点としては、清潔を維持できない、亀裂が入ってしまっている、吸引するのに時間がかかってしまうといった場合には、交換期間を待たずに交換します。
保管方法は浸漬法と乾燥法の2つあります。それぞれ違いをまとめてみました。
浸漬法(ウエット法)
手順としては以下の通りです。
- 気管切開用と口腔・鼻腔内用の吸引カテーテルは分けて保管するため、それぞれカテーテル保管用ボトルを準備します。(気管内は無菌状態のため)
- カテーテル保管ボトルに消毒液を入れます。消毒薬の種類としては7~8%エタノール添加の0.1%塩化ベンザルコニウム(商品名:ヤクゾールE液0.1)や次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)を使用します。消毒液は1~4日おきに交換をします。
- カテーテル内腔を洗浄後、吸引チューブを接続部から外して、消毒液の入ったボトルに保管します。この時接続部がボトルの中に入らないよう注意します。(接続部は手で触れる部分のため、中に入れてしまうと不潔になります)
乾燥法(ドライ法)
洗浄した吸引チューブを乾燥させて保管する方法です。乾燥後はタッパーやペットボトルに入れるまたは吊るして保管をします。
注意点として、乾燥させる際は完全に乾燥させる必要があります。中途半端に乾燥させると細菌が繁殖する可能性があります。
100均グッズを使用した、在宅での収納術をご紹介します!
病院では万能つぼを使用して収納していることが多いですが、在宅にはないことも。
今回は吸引チューブを収納するのに使用できる100均グッズをご紹介します!
- がぶ飲みペットボトルキャップ
- ワンプッシュペットボトルキャップ(広口)
- 500mlのドリンクボトル
- タッパー
- クリップハンガー(ドライ法のみ)
- スマートポット(砂糖などの粉の調味料を入れる入れ物)
- ストローの差し口があるプラスチック製のコップ
- ドレッシングボトル
などがあります。
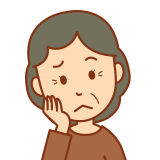
家庭にあるもので使用できるものはありますか?
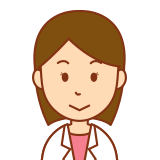
コーヒーの空き瓶、液体洗剤のボトルなどがあります。
その他にも精製水の空きボトル、哺乳瓶を使用される方もいます。
注意点として気管切開用と口腔・鼻腔用でそれぞれ2つ準備してください。気管切開用と口鼻腔用は、分けて使用します。
まとめ
在宅で吸引を行うことになった際、最初にあたる問題かと思います。吸引チューブの交換に関しては病院からの処方、あるいは自分で購入する場合もあり本数に限りがあります。継続的にコストがかかってきますので、チューブの状態に合わせて今回まとめた管理方法を参考に実施してみてください。
またチューブを収納する入れ物にも悩むことが出てくるかと思います。一度購入して長く使用する方法をとるかコストはかかるが都度交換できる方法をとるか悩まれるかと思います。今回紹介したグッズは一部にはなりますが、共通している部分は
- 500mlくらいの大きさ
- 吸引チューブの接続部分が上に出せる
になります。ちなみに、紹介した商品はステーション近くの100円ショップにも売っているものがほとんどでした!
これから先長く使用していくものになります。外出先への持ち運びやすさ、使いやすさ、コスト面などを考慮して検討していただけるとよいかと思います。